
|
マツボックリが木炭になっていたときは、本当にビックリした。
高校生では体験できない炭焼きを体験することができてとてもよかった。また、みんなと一緒に夜を過ごし、炭窯の火をみながら寝袋に入って将来のことを語りあうことがでさたことは良い思い出になっている。
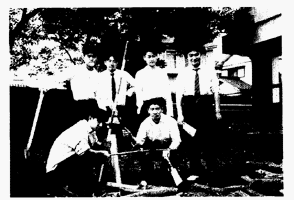
[炭焼きに挑戦した仲間たち]
[先人の知恵に学ぶ]職員
だいぶ長いこと人間をやっていますが、炭焼きを目のあたりに見たのは初めてで、私自身大変な感激でした。しかも、学校の庭で体験できるとは……。
炭焼きの歴史はいつごろから始まったのでしょうか。あの生木が燃え尽きてしまわないで、長時間強力な火力を出す燃料となる。昔の人の知恵って素晴らしいですね。
大きな穴を掘って木を並べ、薪や木ぎれをくべて、そっとふたをし、煙の出方、色合いを気遣いながら、大事に大事に焼けるのを待つ。一時は火力が無くて、かなりの時間小さな穴から交代であおぎ続けたりして、なかなか根気のいる仕事でした。
「良い炭ができるように」と生徒たちも先生方も祈るような気持ちで待っていました。特に、生徒たちの真剣なまなざしが印象的でした。
自分たちの手で「物」を作り出す期待と、中のようすがわからない不安。木炭の出来具合は100%というわけにはいかなかったけれども、生徒たちの充実感は100%以上だったろうと思います。
机の上の勉強だけでなく、身体で味わった貴重な体験は、これからもずっと心に残るでしょう。
6 実践の成果
月例の自然観察会でビックリすることは、移り変わる微妙な変化を動植物は確実に感じ取って、それなりに対応している点です。その発見をすることが喜びにつながります。参加者の生徒も、どのように自然を見つめていったらよいのか、会を重ねるごとに表情が豊かになっていきます。と同時に、積極的にものごとに関わろうとします。
楽しい観察会がモットーです。遊びながら知らず知らずのうちに体得している技−それは一生身について忘れることはありません。
月例観察会での生徒の反応や質問などをこれから紹介していきます。どの観察会でも共通していえることは、子どもの頃の体験が知識となって、行動していることです。そして、子どもの頃の楽しかったことを思い出すかのようにして観察会に参加しています。
現代の高校生であっても、校庭へ連れだして、そこに咲いているタンポポの茎を使って笛をつくり、音がでたら合格などといえば、恥かしそうにしながらも挑戦してみる生徒は何人もいます。音が出ると面白いもので音色のちがうことで飽きることなく吹き続けている生徒もいます。興味がわけば、次に観察のポイントを教えます。セイヨウタンポポとカントウタンポポのちがいは?そして校庭の分布状態を調べてみます。
校庭の生け垣に植栽されている樹木に、千葉県の県木イヌマキがあります。この葉を使って手裏剣を作り忍者ごっこ遊びをします。
前ページ 目次へ 次ページ
|

|